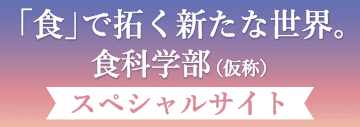日本の4年制大学で唯一の研究室。
野菜や果物などの農産物の包装を研究しています。この領域に特化した常設研究室は、日本の4年制大学では本校のみ。とてもマニアックな研究なのです。もちろん私も、最初から包装に興味があったわけではありません。もともと農産物の栽培などに興味があり、大学および大学院で水耕栽培での生育不良の問題について研究していました。当時は就職が難しい時代でしたので、限られた選択肢のなかからたまたま「農産物の包装の研究員」の募集を見つけました。専門が少し、いや、だいぶ違うような気もしましたが、就職するのに必死だったこともあり、結果、雇っていただくことに。実際に研究してみると戸惑うことも多くありましたが、栽培の学びや経験が活かせる場面もあり、少しずつその魅力を理解していきました。ただ、日本のなかでも珍しいテーマをずっとほぼ1人で研究していたため、孤独感はなかなかのものでした(笑)。
農産物の包装には、大きく2つの役割があります。1つは、腐敗による品質の劣化を抑えること。もう1つは、外部の衝撃などからの損傷を防ぐことです。収穫してから貯蔵、流通を経てお店に陳列されるまで、農産物の品質をできる限り保持します。そのため、温度の違いによる品質の劣化具合を見る貯蔵実験や、落下する高さの違いによる損傷実験など、農産物や包装の種類を日々さまざまに組み替えて研究しています。例えば以前、イチゴをモデルとした損傷研究を行いました。農産物は落下などの1度の大きなダメージで傷むこともあれば、イチゴのように小さなダメージが何回か蓄積することによって傷むものもあります。この損傷評価の理論を研究・発表し、包装を含めたよりよい運び方についての考えを示しました。
このようにこれまでは包装の保護性をメインに研究してきましたが、最近は持ち運びのしやすさといった利便性、中身の特徴などを伝える情報性といった領域にも研究範囲を広げている最中です。
コンビニおにぎりの包装に残った海苔も、フードロス問題の1つ。
農林水産省の統計から試算すると、農産物の流通における廃棄量の区分は野菜類が10~11%、果物類が16~17%です。経済的損失は、合わせて推定約4,000億円。穀類1%、イモ類6%、豆類2%などと比べると、より際立って見えます。この事実を知るだけでも、野菜や果物の包装の研究における社会的意義の高さが理解できますよね。包装の保護性を高めることが、農産物の廃棄量の削減に大きく寄与できるのです。
また最近は、違う切り口からの研究にも力を入れています。例えば、コンビニおにぎりの包装に残った海苔、フタに付いたヨーグルト、クッキーやせんべいの袋に残ったカスなど……他にも、袋や入れ物にほんの少し残ってしまう食べ物は、身のまわりに多く存在しています。これらの包装を工夫することで、フードロスの削減に貢献できないかと考えているのです。たいした量に思えないかもしれませんが、コンビニおにぎりで言えば、年間販売数は数十億個です。ひとつのおにぎりではフィルムの端にある小さな破片でも、日本全体の合計ではものすごい量の海苔が廃棄されていると思いませんか?海苔の生産は海上の広大な面積を使いますし、生産量を増やせばそれだけ海の資源を減らすことになります。包装を通じて海苔のフードロスを考えることは、日本の海を守ることにつながっているとも言えるのです。

包装の視点で一部地域の飢餓を救う。
アメリカは国土が広いため農産物を運ぶ距離も長くなり、トラックを2~3週間走らせることもよくあります。現地ではジャガイモやオレンジを運ぶ際、ろくな包装をせずにとにかく詰め込んで運びます。そのため、下の方にあるものは重さや揺れによる衝撃の影響で運送中に傷んでしまい、結構な数が売り物にならない状態になってしまうのだとか。しかも、それを「仕方ないこと」として流通関係者が受け入れているのは、さらに衝撃的です。この場合、運ぶ際のケースなどを工夫することでかなりの量の廃棄を防ぐことができるはずです。さらにこれを応用することで、一部の地域の飢餓の解決に役立つ可能性があります。例えば道路などの交通インフラが整っていない国や地域においては、農産物をよい状態のまま長距離運ぶのは困難です。したがって、地元地域が不作のときに他の地域から食糧が調達できず、現地の人たちは飢餓に陥ってしまいます。かと言って道路を整備するには莫大な費用がかかる。そこで、包装の視点です。先の話のように運ぶ際のケースなどを工夫して農産物をより長い距離を安定して運べるようにすればいいのです。道路の整備よりもはるかに簡単な話だと思いませんか?つまり包装は、飢餓を減少させるためにも役立つと考えられるのです。もちろん包装にも費用がかかりますし、使った後の廃棄のことも考えないといけませんから、そのバランスは考える必要があります。しかし、安価な農産物だからといって経済性を優先して包装をせず、意図的に農産物が大量に廃棄されているとしたら、どうでしょうか?
近年は環境意識の高まりなどを受け、過剰な包装は避ける傾向があります。もちろん「過剰」はよくありませんが、包装しないほうが絶対によいかと言えば、それは違います。その証拠に、桃の生産・流通・消費・廃棄といった各工程の環境負荷を想定し、梱包資材を使うほうがトータルでの環境負荷が小さくなる可能性を示唆した研究が、直近で発表されています。包装は減らすことではなく、正しく使うことが重要なのです。1つの側面だけで物事を判断せずに、多角的な視点から検証する。研究者としてはもちろん、それ以外の多くの人にとっても大事な考え方だと思います。

食品輸送中の衝撃を計測する装置
学生とのディスカッションをきっかけに、新しい論文を発表。
多角的な視点は、自分で考えることも大切ですが、やはり他人とふれ合うことでより簡単に得られると思います。私もつい最近、学生とのディスカッションのなかで新しい発見をしたばかりです。実験の授業でトマトの呼吸を測定する話をしていたときのこと。これまでは密閉容器内で測定していたのですが、それだとトマトが呼吸を自ら制限してしまい、本来のトマトの呼吸が正しく測定できていないのでは?と気付いたのです。すぐにこの研究をまとめ、論文が日本包装学会の専門誌に掲載されました。研究仲間がいるのは非常に心強いことです。これまでずっとほぼ1人で研究してきた私だからこそ、声を大にして言いたいですね。マニアックなテーマなので心配でしたが、嬉しいことに、私のゼミにも多くの学生が興味を持ってくれ、予定を上回る人数の学生が入ってくれることになりました。自分のテーマに没頭しながらも、ぜひ仲間との交流も意識して研究していってほしいと思います。

食品の保存状況を実験する様子

O2,CO2濃度がわかるガス濃度計
将来のプロフェッショナルの消費者=あなたの視点が重要!
農産物の包装の研究には、農産物の生産の視点、流通の視点、フードロスなどの食の視点など、さまざまなアプローチで研究ができる領域です。家政学部食物学科は、2025年4月より食科学部(仮称・設置構想中)になる(※)こともあって、今後私としては工学的な要素も教えていきたいと思っています。そもそも包装の研究には工学の知識が必要不可欠だと考え、研究者として働きながら工学の博士号を取得した過去があるくらいです。それに、包装は私たちの日々の生活と切っても切り離せないもの。日本女子大学の学生は誰もがこれからプロフェッショナルの消費者になるわけですから、その視点の学びも大きいのではないでしょうか。
包装は、まだまだ可能性にあふれています。ある食品メーカーが商品の外箱をほんの数ミリ短い設計にしただけで、外箱製造時のCO2排出量を大幅に削減できたとの事例もあります。他にも、外箱のない食品やラベルレスのペットボトル飲料が登場するなど、包装はにわかに注目を集めています。そう考えると、改良の余地がある包装は身のまわりにたくさんあるように感じます。これからスーパーなどで食品や農産物を見るときは、ぜひ包装のことも考えてみてください。その包装がどんな社会課題に貢献できるのかも合わせて想像してみると、さらに面白いかもしれませんね。