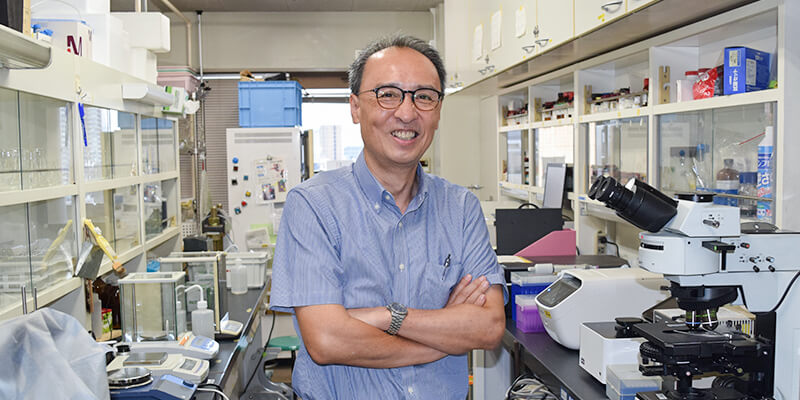実は微生物こそが、地球上で最もメジャーな生物です。
私の専門は生化学で、研究材料として微生物をメインで扱っています。微生物と聞いてイメージされるのは、発酵食品やお酒、ヨーグルトなどを作るのに役立っているといったことでしょうか。もちろんそうした働きも素晴らしいのですが、微生物はもっともっと大きな可能性を秘めた存在であることを、みなさんにぜひ知ってほしいです。
私たちが生きる生態系には大きく3種類の生物がいて、樹木などの「生産者」、人間などの「消費者」、微生物などの「分解者」、と分けられます。「分解者」である微生物がいることによって、動物の死骸や排泄物、腐敗物などは再び「生産者」の栄養源となり、生態系のサイクルが保たれているのです。微生物は存在そのものがサステナブルであり、今盛んに叫ばれているSDGsを考えるうえでも最適な分野のひとつだと言えます。ただ、微生物は目に見えないためなかなか意識されにくく、わかりやすい「生産者」や「消費者」に注目が集まりがちなのです。しかし私は、今起きている感染症の問題や環境問題の多くは、極端な話、微生物たちを軽視し続けたことが要因のひとつだとも考えています。そんな微生物ですが、現在主流となっているドメイン説によれば、微生物こそが生物の大きな集団を構成していることが明白です。それだけ大きな影響力のある分野であるということは強くお伝えしておきたいです。

微生物の働きは、いわば下ごしらえ不要のレトルトカレーを作ること
微生物のすごさは、人間が莫大なエネルギーをかけて実現することを、ごくわずかな力・時間で実現してしまう部分にあります。わかりやすく料理にたとえてみましょう。カレーが食べたいとしますね。普通ならジャガイモやニンジン、肉などを買って、食材を切って、炒めて、煮込んで……と、多くの工程を経て完成します。ただ、レトルトカレーがあれば、温めるだけで食べられます。レトルトカレーも元をたどれば、同じ工程で作られているのですが、微生物は、いわばこの下ごしらえを一気に行い、さあどうぞ、と私たちの目の前に提供してくれるのです。微生物はまさにこのカレーを魔法のようにこしらえる存在で、本来は人間が時間も手間もかけてやらなければいけない多くの工程を、人間に代わって、しかも省力・時短で行ってくれるのです。たとえば、重要な化成品であるアクリルアミドを、微生物の酵素によって生産する方法が日本で開発されましたが、これは従来の化学合成法よりもはるかに簡単であり、今や世界中で実用化されています。
このように、微生物を上手に活用することで、私たちはエネルギーを節約しながら、快適に生活することができるようになるでしょう。加えて、自然環境への負荷が少ないことも大きな魅力のひとつです。今まで化石燃料を大量に使って行っていたことが、微生物という自然界の力を利用して実現できるようになれば、環境問題への貢献度も計り知れないものとなると確信しています。
微生物に紙を作らせて、緑を守り温暖化にブレーキを
近年はSDGsが広まっていることもあり、より社会貢献性の高い研究に注力していきたいと思っています。まず私が考えたのは、森林保護に微生物を役立てられないか、ということです。たどり着いたひとつの答えが「紙」でした。紙は、みなさんご存知のように樹木を原料として作られるため、ここを微生物が代替できれば森林保護に直接貢献できると考えたのです。紙の主成分はセルロースと言うのですが、実はセルロースを作る微生物はすでに存在していて、多くの人はその実力を知っているはずです。若い方は馴染みがないかもしれませんが、ひと昔前に新食感デザートとして流行ったナタデココは、まさにセルロースの塊であり、微生物が生み出していたものなのです。つまり、紙とナタデココは主成分が同じなんですね。現在、紙を作るところまではできているのですが、どうしてもコスト面で折り合いがつかず、技術革新をめざしている段階なので、ぜひ頭のやわらかい学生たちの知恵を借りて研究を進めていきたいと思っています。
この研究は食品ロスの観点でも重要な意味を持つと考えています。この微生物は、簡単に言えば炭水化物を食べてセルロースを作ります。そのため、コーンスターチを作る際に出るトウモロコシのかすやサトウキビのかすなどが利用でき、産業における食品ロス低減にも貢献できるのです。同じようにして、残飯や廃棄されるコンビニ弁当などもこの微生物に食べてもらうことで、ゴミを資源とした持続可能なサイクルを実現できます。大学の学食や近所のコンビニとの協力なども視野に入れながら、この研究が進めば「コンビニの廃棄弁当で地球を守っている」なんてことが、堂々と言えるようになるかもしれません。
また、現在私たちの研究室では、汚れた水をきれいにしてくれる微生物も研究しています。特に工場から出る汚染水の処理は、現在も大きな費用やエネルギーをかけて行なっているので、そこに微生物を活用することで地球の水環境も守っていきたいと考えています。
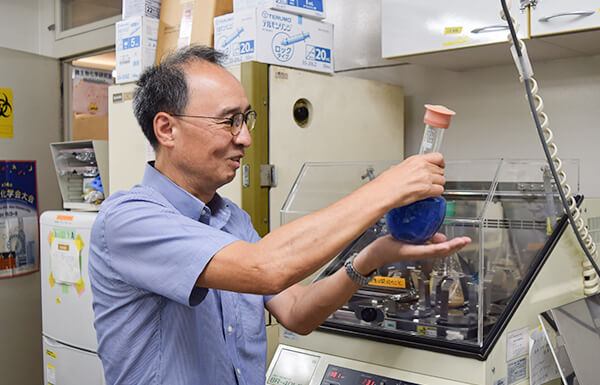
培養中の微生物の様子をチェック。日々の観察はとても重要です。

微生物が作ったセルロースのシート。これを乾燥すると紙のようになります。
微生物研究のおもしろさは、偶然性にある。
この研究の醍醐味としては、偶然性も大きな要素のひとつと言えるかもしれません。数年前、大村智博士にノーベル賞が授与されるきっかけとなった寄生虫駆除剤イベルメクチンは、博士が何の変哲もないゴルフ場の土を採取し、たまたまそこにいた微生物が生産する物質を糸口に作られました。第二次大戦で多くの命を救ったペニシリンの発見は、ブドウ球菌を培養中に偶然アオカビが混ざってしまったことが始まりと言われていますし、こうした例は枚挙にいとまがありません。私自身も、固まっているはずの寒天プレートがなぜか溶けてしまう現象に出会い、新たな微生物を発見し、そこから今まで誰も知らなかった酵素を見つけたことがあります。そんなことがきっかけでノーベル賞につながることだって、決して夢ではないのです。
夏休みやお正月休みがちゃんととれる「人にやさしい研究」です。
もちろん微生物の「研究」ですから、地道な作業を支える根気も必要不可欠です。以前、とある大学院生の修士論文を指導していたのですが、彼女は2年生の11月頃まで目的の微生物が見つけられていませんでした。そこで私は「発見は諦めて、今ここにあるデータだけでまとめたほうがいい」と助言したのですが、彼女は諦めませんでした。結果、なんとその翌月に目的の微生物を発見したのです。急いで内容をまとめて論文内に入れ込み、なんとか完成することができました。諦めないことの大切さ、研究のおもしろさを再認識させられた出来事でした。
ただそれでも、私は微生物研究は、自由にアレンジが可能で、人にやさしい研究だと考えています。マウスなどの動物と違ってコンパクトで扱いやすく、生命のサイクルが早いので結果をスピーディーに得ることが可能です。また、低温で保存することで冬眠させ、自分の好きなタイミングで実験を再開させることができるため、夏休みやお正月休みをきちんと取得できる点もありがたいポイントです。将来、子育てしながら自分の仕事を持ち続けたい、という方にも適していると思います。
SDGsで示されているように、これからはさまざまな社会課題に向き合って生きていくことが大切になる時代です。加えて、多様なライフスタイルも尊重されなければなりません。微生物の研究は、さきにお話しした研究内容のように、社会課題解決に直結します。そこへの貢献を大きな目標としながらも、根気よく、楽しく、柔軟な発想で研究を続けていける人を、より多く育てていけたらと思っています。