黒人女性の豊かな創造力を、もっと多くの人に知ってほしい。
専門はアメリカ文学で、特に、黒人やアジア系、先住民などの女性文学を中心に研究してきました。私が学生だった頃、ちょうど多くの女性作家の作品が日本でも紹介され始めていた タイミングでした。もともと小説が好きだったのですが、その頃アメリカの黒人女性作家トニ・モリスンの「青い眼がほしい」を読み、今まで読んだことのなかった独特の作品世界に魅了されました(モリスンはその後ノーベル文学賞を、米国の黒人女性として初めて受賞しています)。それから黒人女性を中心としたマイノリティ作家の作品をたくさん読むようになりました。そして彼女たちの豊かな創造の世界をもっと深く知りたい、という気持ちから研究者という道を志した次第です。
高校生のときにアメリカ留学をしていた経験があり、ホームステイ先が黒人の家庭でした。そのため、それがきっかけとなって黒人女性文学を研究しているのではと言われることがあるのですが、違います。私が研究している理由は、単純に黒人女性の作品が文学として面白いと思ったからです。ただ、ホームステイに何も意味がなかったわけではありません。その家族の私からすれば曾祖母にあたる世代に奴隷だった人がいたこと、今も続く色々な差別、その中で生き延びてきた人々の歴史などについて、よりリアリティをもって知ることができました。おかげで、女性作家のバックグラウンドを深く理解するのに役立ち、作品を読む面白さが増したのです。近年は黒人女性だけでなく、白人側がどのような人種観を抱いていたのかにも興味を抱いており、研究対象が広がっています。


ネイティブ・アメリカンの作家レズリー・マーモン・シルコウの故郷を訪問
マイノリティ作家の文学は、社会の不平等に気づかせてくれる。
作家が文章を書く原動力として、正義感や倫理観が挙げられます。マイノリティ作家の作品には、「差別反対」を訴える目的で書かれたものも多いのですが、そうでなくても、優れた作品であればマイノリティとして生きる現実が何らかの形で反映されていることは言うまでもありません。登場人物が怒ったり嘆いたりするだけでなく、やり過ごしたりあきらめてしまったりという場面を共感しながら丁寧に読んでいくうちに、いつのまにか社会の不平等や差別に気づいていくことになるでしょう。
「不平等はいけません」「差別してはいけません」と言うのは簡単で、むしろ誰もが当たり前のことだと思っていますよね。でも、社会にはさまざまな形をした多くの不平等があることを、文学はなまなましい形で教えてくれるのです。
マイノリティ女性の文学作品が世に多く出始めた1980年代。彼女たちの埋もれていた過去の作品を再発見して文化的価値を見直そうという動きが、アメリカで起こりました。実際に読むと面白い作品は多いのに、なぜこれまで評価されてこなかったのか。その一因は、評価してきた側がほぼ白人男性だったためとも考えられています。その結果、1990年代初頭にかけて大学などの文学を学ぶ現場でマイノリティ作家や女性作家の作品をより多く取り扱うようになるなど、カリキュラムも大きく変化しました。もちろん、ただ作家の人種や性別の人数バランスがとれればいいというものではないので、その手の議論も散々行われた結果、今日に至っています。従来の研究や教育では光を当てられることのなかった男女のマイノリティ作家が今や必読とされていますし、トニ・モリスンの作品などは何度もベストセラーになり書店にも必ず置かれています。そのような変化は素晴らしいことだと思います。
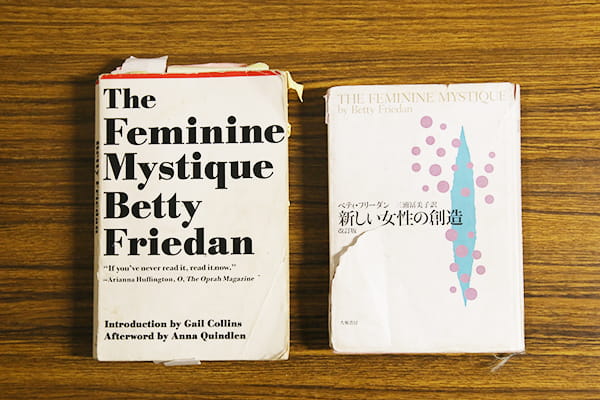
アメリカ女性解放運動の代表的指導者ベティ・フリーダンの原著と翻訳本
日系人も強制収容所に押し込められていた。
強制収容所と聞くと、ナチス・ドイツでの出来事を思い浮かべる人が大半かと思います。実はアメリカでも、第二次世界大戦中、日系人は敵とみなされて強制収容所に押し込められていたのです。日系人の歴史や文化を研究する際、この強制収容所体験は避けて通れない事実です。
収容所とされる施設は、砂漠の中のほったて小屋。ライフルを持った兵士が常に見張っている状態です。そこから出る方法のひとつが、アメリカに忠誠を誓い、従軍して戦うことでした。多くの日系人が従軍を選択する一方、自分たちの自由を奪った合衆国に忠誠を誓うことも兵士となることも拒否する日系人もいて、収容所内の日系人社会は分断され、若い世代の日系人は「アメリカ人」というアイデンティティを根底から奪われる強烈な危機を経験することになります。日系人作家ジョン・オカダの小説『ノー・ノー・ボーイ』は収容所体験を生き延びたそのような世代の、戦後のアメリカ社会での暗中模索を描いた名作です。日本にルーツを持つというだけで自由も財産も奪われ、強制収容所に監禁されるー今の日本で平和の中で生活している日本人には想像もつかない世界だと思います。だからこそ、このような作品を読み、深く理解し、また登場人物に共感することは、平和を考えるうえで重要な役割を果たすことができると考えています。
いじめられる側にも、いじめる側にも共感を。
主人公は11才の黒人少女。学校に行けばいじめられ、白人のように色白な子がチヤホヤされている。父は失業中、両親は毎日喧嘩ばかり。主人公は子ども心に「私がもっとかわいければいじめられないし、親ももっとやさしくしてくれて、夫婦喧嘩だってしないはず」と思い込む。そして神様に「せめて眼だけでも、白人のような青い眼にしてください」とお願いする。
最初にお話ししたトニ・モリスンの「青い眼がほしい」の冒頭の部分です。この小説は学生にも勧めています。ここは女子大ということもあり、学生はとてもいい読み方をしてくれます。特に「自分がもっとかわいかったら」と願う主人公には、多くの学生が理解を示します。今の日本の社会は、女性にとってかわいいかどうかが大変重要で、「自分がもっとかわいければよかったのに」と思った経験が大半の女性にあるからです。黒人でなくても、私たちは少女の「青い眼がほしい」という切実な思いに共感できるのです。日本で生きている日本人にはありえないような不幸な人物を描いているのにもかかわらず、多くの読者の共感を得られている点は、この物語の魅力の1つです。
ストーリーの中盤、最初は主人公に親切だった少女が、いじめる側になります。その少女は黒人ですが、主人公より肌の色が薄いのです。「自分はこの子とは違う」「自分はこんなに黒くない」と距離をおくことで自分を守っていたのではないか。彼女が嫌ったのは主人公というより、主人公の中に見えてしまう自分自身の姿だったのではないか、とレポートに書いてきた学生がいます。単に「いじめはよくない」ではなく、かといって「いじめる側の気持ちもわかる」だけではない、人間の心の内面に踏み込んだ素晴らしい洞察だと思います。
こういった物語の感想として「いじめる側がひどい」「いじめられてかわいそう」などと、短絡的に終わらせてしまいがちです。大切なのは、もしかしたら自分が被害者、もしくは加害者になってしまうかもしれないという想像力を持ち、認識を深めること。そのためには、物語の背景を理解し、丁寧に読み込む必要があります。すぐれた作品にはそうするだけの価値が十分にあります。あらすじを追うだけではできないことで、細部まで味わいながらゆっくり、深く読み込むからこそ、違う時代に遠い国で生まれた物語が、現代の私たちの知恵や力になってくれるのです。

文学は、必ずあなたの役に立つ。
昨今、小説は何のために読むのかと、疑問を抱く人が増えているように感じます。アメリカでもキリスト教の影響で「小説を読むことは娯楽に時間を無駄使いすることで、罪である」と考えられていたこともあります。
でも、それは違います。たしかに文学作品には、社会課題を解決する解答は書かれていません。それでも国や人、ジェンダーの平等を考えるなら、他の国や人の立場になって考える想像力が必要不可欠です。多様な国や人の文化、考え方、感じ方を文学上で体験することで、その想像力は身につきます。文学からでしか得られない知見が確実にあり、文学は私たちの生きる世界を持続させていく知恵を継承していく大切なツールなのです。
黒人女性の詩人オードリー・ロードは「詩は贅沢品ではなく、むしろすべての人の生きるための力として書かれ、読まれ、シェアされるべきもの」と書いています。日本に住んでいると、海外を知らなくても、英語ができなくても、新聞すら読まなくてもそれなりに生きていけるでしょう。でもSDGsをはじめとして、私たちが暮らす世の中には社会課題が山積していて、いつ危急の問題として目の前に現れるかわかりません。その備えとしても、文学が有効であることを知っておいてほしいのです。少しでも面白そうな本を見つけたら、ぜひ読んでみてください。明日かもしれないし、何年後かもしれない。でもそこで得たものが必ずあなたの役に立つことを、ここに断言しておきます。
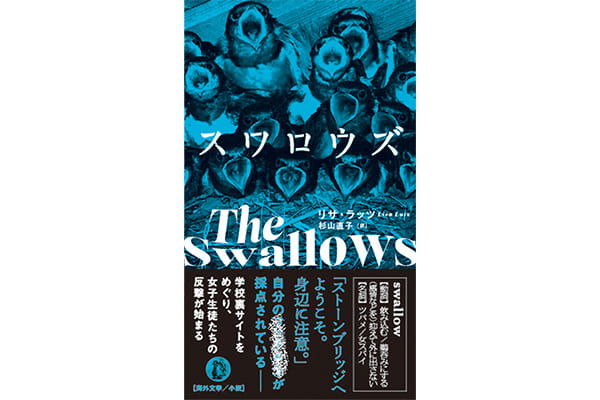
最近翻訳にも力をいれています。上記書籍の情報はこちら

