外国ルーツの子と言えば「日本語の問題」と考えるのは間違い。
学校臨床学が専門です。外国ルーツの子どもをはじめとした、教育におけるマイノリティを支援する研究に力を入れています。ただ、もともとめざしていたのは研究者ではなく、教員でした。教員養成系の大学での学びを経て、数学の教師として中学校に配属されます。そこはいわゆる荒れた学校でした。教室に行くと、私のことは気にも留めず、数人の生徒がロッカーや机の上で足をブラブラさせながら談笑していたんです。まるで昔の学園ドラマのワンシーンでした(笑)。それでも、荒れた生徒たちとうまくコミュニケーションをとることで、少しずつ授業が成立するようになっていきました。ただ、問題はここからです。いざ授業に取り組んでも、その生徒たちはなかなか内容についていけないので、いつしか「できる子」たちから邪魔者扱いされるように。そうなれば、教室にかれらの居場所はなくなります。このサイクルは、数年経って配属する学校が変わっても、同じように繰り返されました。それは、例えば不登校の生徒など「うまくいかない子」たちにも同じような傾向が見られました。そこで気がついたのは、先生たちの多くは「できる子」を基準に考えていて、そうでない子は足を引っ張る存在として認識しているということです。学校は「みんなのもの」ではなかったんです。それに気がついてしまったことは、かなりショックなことでした。それで、現場を離れ、もう一度学び直すことにしました。
その後大学院で取り組んだのが、その子どもの教育についての研究です。1980年代後半から、日本に長期滞在する外国人が急速に増え始めました。いわゆるニューカマーです。その移動に伴い、外国人の子どもたちも日本の公立学校に通うようになるのですが、「移民」として受け入れる体制を作らない日本社会では、十分な学びの機会を得られていないのです。それだけでなく、外国ルーツの子どもは日本語さえできれば他に問題はないという思い込みから、かれらが抱える様々な葛藤も「日本語の問題」と処理されてしまっていたのです。だから、日本語に少しでも遅れが見られれば、まるで学力が低いかのようにみなされ、自己肯定感を低めてしまっていたのです。その子がどんな状況にあり、何が必要かを把握し、それに対応しながら必要な学びの世界を開いていくこと、それこそが質の高い教育なのです。ですから、初任で私が出会ったヤンチャな生徒にも、そして不登校の生徒、外国ルーツの生徒、障がいがある生徒、いずれの生徒にも、そうした質の高い教育が提供される必要があると考えています。


ベトナム訪問の様子
復興支援のメッセージが、被災地の子どもを追い詰める。
2011年3月11日、東日本大震災が起きたときのこと。個人的に居ても立ってもいられず、4月2日からNPOの活動を通して毎週末現地に支援に行っていました。多くの犠牲者が出たことはもちろん、残された人々も深い悲しみの中にあったと感じます。そうした中で、子どもたちはどうやって生きていくのか、それがとても気になりました。知人や友人、家族を亡くしている子どももいるなか、教科書は津波で流され、教室は泥まみれ。精神的にも物理的にも、教育を受けたくても受けられない。あるいは、教育を受けた方がいいとは思うけど、その気になれない。そこには、さまざまにダメージを受けた子どもたちがいて、そこからの回復にも個人差がある。でも、周囲は待ってくれないのです。学習の時期を遅らせることができるわけでもなく、受験のタイミングだってそのまま。おまけに世間は何の悪気も感じずに「復興に向けてがんばろう!」とメッセージを発信します。これは実は、現地の子どもたちにとって「早く普通の学習のペースに追いつけ」とプレッシャーをかけられているのと同じなのです。
ここに、日本社会の課題を感じました。日本では「普通」であることが重視されます。現役で高校、大学に入り、安定した企業で働き、結婚して子どもを産んで……自分の親の育て方にそんな期待を感じる人も多いのではないでしょうか。この理想のレールを少しでも踏み外すと、世間から変わり者と思われてしまう。そんな前提の中の「誰一人取り残さない」というスローガンは、みなが「普通」になることを求めているように聞こえてくるのだと思います。
SDGsには「質の高い教育をみんなに」と書かれていますが、それは、今日の受験で測られている学力を高めることを意味すると、私は考えていません。個人個人のペースに合わせ、時には休んだりしながら、誰もがそれぞれに必要だと考えることを学んでいける場がある。もし「誰一人取り残さない」という言葉を使いたいのであれば、それは、学びたいことを学びたいときに学べる場を作れるようなゆるさを許容することによって、自ずと「誰一人取り残さない」という状況が作り出されることだと思います。長い人生、悩んだり立ち止まったりする時期だって必要でしょう。まずは日本社会全体が、急がせない、慌てさせない、そんなゆるさをもっと許容していく必要があると感じています。


フィールドワークの様子
あなたが悪いと思わせる社会が問題。
ゆるさが許容されない日本社会がもたらす課題は、大学生と出会う中でも感じることです。ICTをテーマに卒論を書きたいと話すゼミ生がいました。ところが、ICTに関する資料や文献をいくら調べても、腑に落ちないような、乗り気にならない感じが続き、ついには「書けない」と言って泣き出してしまったことがあります。そんな時「何なら書けそうなのか」という私からの問いかけに、それには答えず、その学生は家族の話を始めたのです。彼女の家は3世代同居で小さいころから祖父母の権限が非常に強いというのです。それは例えば、2階にいても1階で祖母がご飯を用意している音がしたら、呼ばれる前に降りていかなければならず、それをしないと祖母の機嫌がずっと悪い。「手伝ってほしい」と言われることは決してなく、求められるのは気を利かすこと。それを損ねたら自分の責任。いずれかのタイミングで彼女が謝りに行くまで、その不機嫌は続く。しかも、なぜか兄はそうした対応を求められない。求められているのは自分だけ。その理不尽を両親に伝えても「あなたが悪い」と返されるだけ。あふれるように語られる話を聞いている中で「それを卒論にしたら」と私は問いかけました。それから彼女は自分の経験を研究対象とする当事者研究をスタートさせ、その後、大学院にも進学して、ジェンダーや家族の問題に関する研究を深めていくことになりました。
この学生もそうでしたし、研究対象としているマイノリティの子たちもそうですが、何か問題があるとすぐに「自分が悪い」と自責思考をしてしまい、それによって自分の殻に閉じこもりがちになります。親の望むように生きられない自分が悪い、家族を愛せない自分が悪い、といった具合で。社会学には「個人的なことは政治的なこと」という言葉があり、個人に降りかかった問題を単に個人的なこととして済ますのではなく、社会的なこと、社会構造によって引き起こされた問題として捉えたうえで、よりよい社会を作っていくために、何を変えていったらいいかを考えていくという志向性があります。ですから、先の学生のように、「自分が悪い」という理解のもとで自分を責め続ける学生に対し、問題は周辺環境からもたらされること、その環境とはいかなるものなのかを考えるという研究活動をすることを勧めています。「あなたは悪くない。そう思わせる社会の側に問題があるんだよ。それが何かを分析できるといいよね」と。
近年は女性や子どもの自殺が増えていて、マイノリティの位置にあるものがさらに追い詰められていると感じます。自殺は、暴力という負のエネルギーが内側に向かっているのだと思います。若いころに出会ったヤンチャな生徒は見た目や言動は荒れていましたが、自殺するイメージはありません。暴力という負のエネルギーが外に向けていたからではないかと思います。そう考えると、暴力という負のエネルギーが生み出される社会構造を問題にする必要があり、研究者としてもそれを明らかにしていく使命がありますが、生徒や学生たちにも「個人的なことは政治的なこと」という視点で、社会を見つめる力を養ってほしいと思っています。

問題が多い今の時代こそ、女子大で学ぶ意義は大きい。
日本社会は依然として分離教育が進められています。少しでも同じようにできない子どもには「障がい」のレッテルが貼られ、「特別支援」という枠組みで、別の場所で学ぶことがよいこととされています。こうして進められてきた分離教育は、かなり前から国連からも批判されています。子どもの頃に障がい者と接する機会が少ないと、そうした人がいない社会を当たり前と考えてしまう可能性も高くなります。多様な人が一緒に学ぶことで、社会にはいろいろな人がいることも学べます。教育は、障がいの有無で学ぶ場を分ける必要はないと思います。
ただ、本校は男子のいない女子大学。分離教育といえばそうです。そこに意義はあるのでしょうか??この点は、声を大にして「ある」と言いたい。
例えば、先ほどの学生の話。会話の場にひとりでも男子がいたら、果たしてありのままに話せたでしょうか。涙を流せたでしょうか。男子がいる場での女子の涙は、別の解釈を呼び込む文脈を作り出したりします。それは今の日本社会に女性やセクシャルマイノリティの視点が足りていないために起きてしまう問題とも言えます。ジェンダーギャップが縮まるまでは、女子大で学ぶことの意義は大きいと思います。
最近、私のゼミには、自分自身の体験を研究する、いわゆる当事者研究をする学生が増えています。体験の原因や背景を探っていくと、おのずと社会構造の問題にたどり着きます。学びのなかで社会の問題をつかむことができれば、次はそれを解決する方向に向かって考え行動するだけ。今、世界はSDGsなどを掲げ、少しずつ変わろうとしています。でも、まだまだその力は十分ではありません。本科で教育をめぐる課題を多面的に捉えることで、公正な社会を目指して変えていける力を身につけ、将来はそれを現場で実践していけるような人になっていってほしいと思っています。
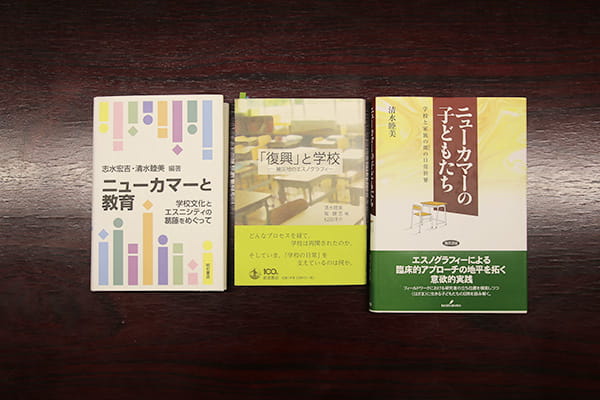
清水先生の著書の一部

