フードロス問題を「もったいない」で語る時代は終わりました。
食べられるのに処分されてしまう食品、つまり「フードロス」問題について研究しています。
幼少期、実家の庭でいくつか果物が採れたので、多少見た目が悪くでも味が変わらないことは知っていました。それに、もぎたてのフルーツは本当に美味しいんですよ。なのに果物の流通販売では、味がよくても傷があるものや、大きさが不揃いのものは売り物になりません。見た目優先で熟す前に出荷するから、もぎたてに比べれば味は落ちます。「なぜ美味しいものが売れないんだろう?」と考えたとき自分の学生時代を思い出しました。本格的なバンド活動をしていたのですが、世の中から見向きもされず、なぜ自分の音楽が理解されないのかと苦悩した日々を。美味しいのに売れないフルーツは、自分と同じだ、と思ったんですね。そんな極めて個人的なことから研究の興味は食品の流通、マーケティングなどへと広がっていき、価値あるものが捨てられている現状をどのように理解したらよいのかというテーマにつながっています。
現在は主に食を扱う企業に聞き取り調査や共同プロジェクトを通じて、集まったデータをもとにフードロス問題の解決策を考えています。一般的には消費者の「もったいない精神」に訴えかける手法がとられがちですが、多くの場合、短期的に効果があっても長続きはしません。「とにかく食べ物は残さないように」といった、一方的に無理や我慢を強いるスタイルはストレスがたまるからです。特定の人だけが辛い思いをするのではなく皆で協力し合うことが大切なのです。個人的には、ほとんどのフードロス問題は不完全なコミュニケーションに起因すると確信しています。身近な例で言えば、家族が作ってくれた晩ご飯を黙って残すこと。もし体調が悪くてあまり食べられそうもないと分かっていれば、事前に「体調が悪いので今日はいつもの半分にしてほしい」と伝えておけばいいわけです。逆に作り手が察して食べられそうか聞くことだってできるでしょう。作った家族だって食べてくれなかったら悲しい思いをします。先に聞いていたらそうはならなかったということですね。また先日、ある飲食店でお腹がいっぱいになり持ち帰りをしたところ、もらった容器に店主からの気遣いのメッセージが書かれていました。ちょっとしたことですがやっぱり嬉しいことですし、これも大切なコミュニケーションの1つです。家族間や飲食店とのやりとりに比べれば、企業同士となると難しいことも多いのですが、基本は変わりません。フードロス問題の研究とは、どんなコミュニケーションがより有効なのかを考えることでもあると思っています。
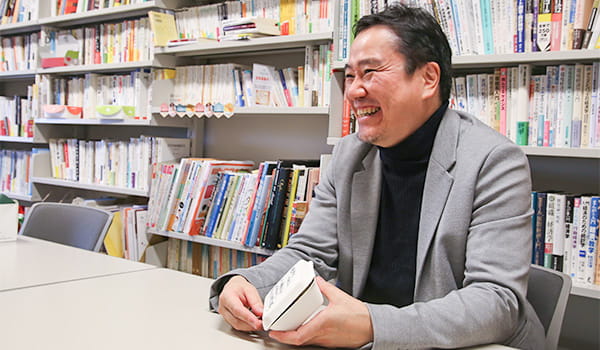
手書きのメッセージが書かれたお持ち帰り用の箱は、研究資料として大事に保管している。
捨てることを前提として仕入れている商品もある。
企業におけるフードロスは需要に対して作りすぎ、仕入れすぎが原因で起きますが、事情は複雑です。大学院時代に、とある小売店で特定の商品を毎日必ず200個余らせて廃棄することをルール化していると聞いたときは驚いてすぐに論文を書きました。一度でも品切れを起こすと、お客さんに「商品がないお店」とのイメージがつき、以降来店してもらえなくなるかもしれないというプレッシャーがあるのです。品切れに罰則を設けている企業もありました。調査を進めると、多くの場合、このように廃棄を前提とした商品はパンやケーキなどの原価が低く利益が大きいものによくみられることが分かってきました。つまりは、足りなくなるよりも余らせるほうが儲かるため、フードロスが発生しているということなのです。私たちは仕入れすぎをただのミスだと思っていましたが、そうではない。わざと仕入れすぎているというわけなんです。
実はこの仕組み、お客さんの満足度やお店の利益など、皆にとって最適な、ビジネス上は正しい選択といえます。でも、やっぱり気持ちのいいものではありませんね。あるスーパーでは、パンを大量に廃棄する担当者が精神を病んでしまったと聞きます。少しでも良心があれば胸が痛むのは当然ですよね。また環境面に目を向ければ、輸送に余計な燃料を使うこと、焼却処分をする量が増えることは、どちらも温室効果ガスの排出量増加につながります。作った人にしてもいい気分はしませんし、仕事のやる気にかかわる経営上の重大な問題になるときもあります。いくら経済的に正しくても長い目で見ると、フードロスはやはり減らしていくべきでしょう。
一方、フードロス問題が起こるということは恵まれた国の証ともいえます。捨てるほど食料がたくさんあるということですから。実際、発展途上国では特に家庭からの食品ロスは少ない傾向にあります。だからこそフードロスを完全な悪だと切り捨てずに、必要悪という側面もある食品廃棄の動向や、ストレスが多い消費者の行動を冷静に分析しながら、根本的な原因とそれに対する現実的な解決策を見出すことが求められます。そのためにもまずは現場に足を運んで、現実に起きていることを正確に把握するよう学生にはアドバイスしています。
食べ残しの持ち帰り行為を、もっとオシャレに!
現在私のゼミ生には3年生が主体となって飲食店を回り、食べ残しの持ち帰り行為の普及に取り組んでもらっています。日本では衛生的な問題で持ち帰りをNGとするお店が少なくありません。持ち帰ったお客さんからのクレームを恐れて禁止しているため、普及していないという一面があるのです。本来、お店では問題のなかった食べ物で食中毒を起こすのは、消費者の管理方法に問題があるわけですから、お店が責任を取る必要はないはずです。消費者にしてもデータをとると大半は持ち帰りたいと感じていることが分かっています。それらのことを私たちが代弁すべく、消費者の自己責任での料理の持ち帰りを推奨するステッカーを配って、お店に貼ってもらう活動をしています。
この活動は、ドギーバッグ普及委員会という非営利活動の一環として行っています。ドギーバッグとはテイクアウト容器のこと。現在はよりよい容器の開発をめざし、折り方やサイズ、素材についても紙、プラ、環境にやさしいものから電子レンジで使えるものまで、サンプルをいくつも作って試行錯誤をしています。そして最終的には、食べ残しの持ち帰り自体をオシャレな行為だと思ってもらうことが必要だと考えています。普及委員会と環境省、農林水産省、消費者庁の共催で、2020年にドギーバッグというネーミングを新しくしようと公募がありました。私も審査に加わりましたが、その結果「mottECO(モッテコ)」が採用されました。「もっとエコ」「持って帰ろう」というメッセージが込められているそうですが、有名なファミリーレストランやホテルなどでも少しずつ浸透しています。今後私たちとしては、学生に容器デザインをしてもらったり企業とのコラボレーションを進めて、持ち帰り=オシャレというイメージづくりのお手伝いができればと思っています。

試作をしたドギーバッグの数々

学生たちと活動しているときの配布物の一例
食のこと以外を考えることも大切。
経済学はお金について考える学問ですが、本科では金銭的評価のしづらい消費者の行動や社会の仕組み、コミュニケーションの問題などにも積極的にスポットを当てています。特にフードロスの問題は、生産から消費に至るまで、経済、経営、環境も含めて生活者と世の中のさまざまな要素との複雑な関係性を取り上げます。これだけ幅広い問題を総合的に考えられることは、本科で学ぶ醍醐味と言えるでしょう。扱うテーマも食のことばかりではありません。むしろ食だけにこだわりすぎると、フードロスの問題は本質を見失う可能性すらあります。例えば、世界には出された料理を残すほうがよいとされたり、肉を食べられない国もあるなど、この問題は地域ごとの食に関する文化や宗教、習慣などから考えることも大切です。
ただし「フードロスにはいろいろな問題がある」で終わらせてほしくないですね。広く学ぶなかでも自分なりにきちんと答えを導き出して、それを人に伝えることにチャレンジしてほしいと思っています。特に今の日本の社会は周囲からの批判を恐れてか、匿名のSNSはともかく、公の場では自分の考えを曖昧にしがちです。そんな調子で変化の早い今の世の中に放り出されると、自分を見失ってしまうことになるでしょう。自分で考えたことを包み隠さず伝え、自分と周りの人とのポジションの違いを自覚しながら関与してゆく。そんな本気のコミュニケーションが、フードロス問題、ひいては私たちがより幸せに暮らしていくために必要なことなのではないでしょうか。

