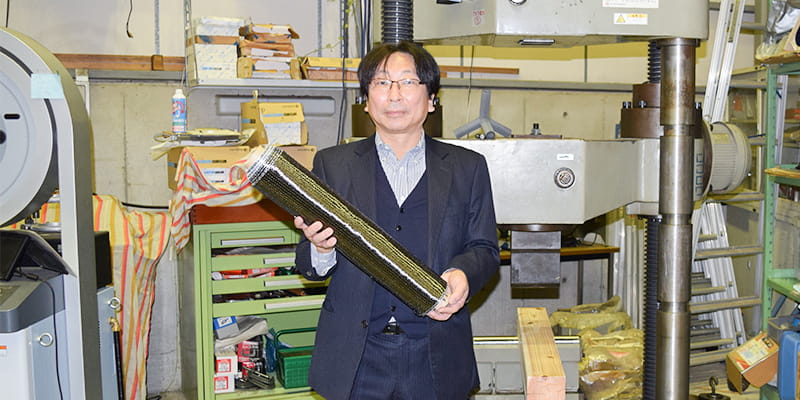五重塔の揺れを計測し、その性状を知る!
私は建築の構造デザイン、つまり建物の骨組みを考える専門家です。高層施設や戸建て住宅など、実際の建築に携わることもあれば、既存の建物の安全性確認や修繕なども行います。そうした修繕活動としては、これまで清水寺、善光寺、世界遺産となった富岡製糸場西置繭所などにも携わってきました。また、建築に使えそうな新素材や新工法の開発にも取り組んでいて、多くの企業と一緒になって進めています。
多岐に渡る私の活動ですが、学生には基本、その活動をできるだけ伝えるようにしています。なるべく多くのことを提示することで、興味を持つきっかけを与えたいからです。根底には、自分で興味を持ったことに対して、自分で掘り下げていける主体性を身につけてほしいという学生への願いがあります。私はただその後押しをするだけなのです。だからこそ、勉強や研究をするうえで何か私が助けになるのであれば積極的に協力しますし、何事も実際に見たりふれたりすることが大切なので、現地調査に一緒に行くことも少なくありません。
たとえば先日ある学生から、私の活動のひとつであった五重塔に関することを研究対象にしたいと申し出がありました。どんな研究にするかを一緒に考えたところ、五重塔に振動計を設置し、どのくらいの風でどのくらい揺れるのかを計測することで、建物の強さを評価しようということになりました。ちなみにこの振動計も、私がNEXCOと一緒にやっている高速道路の地震の影響調査に用いているものです。現地の調査にも同行するなど学生をフルサポートした甲斐があってか、風によって振動する性状の興味深い研究データーを得ることができました。この詳細は、学生が論文にまとめ更に研究を進めているところです。

五重の塔で実施調査を行った際の記念写真
歴史的建造物の補強活動、それは歴史の1ページに過ぎない。
伝統的な建物の保存・補強活動のなかでも、富岡製糸場の西置繭庫ではいろいろ経験をさせて貰いました。明治期の煉瓦の試験では、木材の強度とそれ程変わらない煉瓦であった事や木造の枠にしっかりと煉瓦が固定されていると非常に丈夫であること等、実験や実大の振動実験により多くの知見を得ることができました。そして、多くの文献を参考に煉瓦造の挙動を把握して、多様な調査手法、解析手法を駆使し、総合的な判断をして、活用や保存を考えた先進的なプロジェクトになりました。
こうした活動はいかにも多くの最新技術があってこそ成り立つイメージもありますが、実は何百年もの間、定期的に補修・補強は行われてきました。だからこそ今もこうして残っているとも言えます。ある歴史的建造物は、一見不安定な地形に立っていたのですが、地層を見てみると、人工的に消石灰などを固めた、今で言うコンクリートのような層がいくつも積み重なっており、昔の人々がこの地を補強してきた歴史を知ることができました。建物も周辺の土地も、補強・補修活動は脈々と続いてきており、たまたま私がそれを続けさせてもらったというだけなのです。
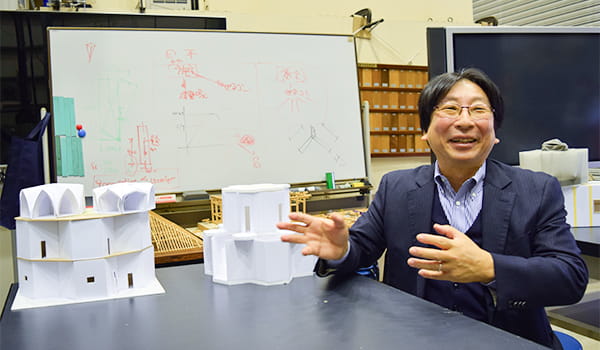
800年後の建て替えのために、木を植えていた!?
建築に関する昔の人の偉大さを感じた例がもうひとつあります。現在、建築家の隈研吾さんと一緒に、ある神社の建築プロジェクトを進めており、その過程での出来事です。使用する木材を探すため、日本でも随一の木材収集家を訪ねたときのことでした。さまざまな種類の木材があるなかから、ひときわ色ツヤがよく目が詰まったものを見つけ、それを使うことにしたのです。後日、その木材を知るために、地元の林業センターで相談したり文献を調査したりした結果、驚きの事実が判明します。なんとその木は、約800年前に「将来神社を建て替えるときに使うために、神社の参道に植樹された木」だったのです! そのうちの1本が台風の影響で倒木し、たまたま収集家の手元にあったこともわかりました。
現代で建築と聞くと、なんとなく自然を壊して建てるようなイメージがあります。ところが昔は、その土地で育った材を生かし、それが将来に渡って持続可能なものであるよう考えて建築していたということが、この話からもわかります。昔の人はSDGsなんて言われなくても、あたり前のようにそれを実行していたんですね。
木材をもっと使うために、新素材を開発する。
現在私は、構造技術者協会の地球環境問題担当理事ということもあり、建物に木をたくさん使うことを推奨し、普及させる活動もしています。これは、CO2排出量の削減や山林、林業の保護などを目的に、近年法律でも定められました。この活動においては、木造建築を促す「木造化」と、鉄骨造やRC造にもなるべく木を組み込むことを促す「木質化」の2つの言葉を使っています。建物をすべて木造にすることは不可能なので、今後はどこまで木質化を進められるかが重要です。
そうした木質化が推進できる、もしくはそれと同等以上の効果が期待できる、新素材の開発には大きな意味があります。たとえば、チタンです。鉄と比べれば重量は約3分の1です。鉄に比べると熱伝導率が低く、熱容量も小さいので、密着する素材と常に同じ温度でいられるため、結露が生じません。木と鉄が密着する場合は、結露で木は腐り、鉄は錆びてしまうのです。そこで今はチタン製の釘を開発するなどして、木質化をサポートしています。さらに、チタンは半永久的に腐らないので、何万年というオーダーにも耐えます。最初の製造エネルギーは大きいのですが、トータルで考えれば非常にサステナブルな素材であると言えるのです。
同様の素材として、炭素繊維にも注目です。いわゆるカーボンのことで、軽くて強い特徴を生かし、自転車のフレームや航空機のボディなどに使用されています。こちらは鉄と比べて重量は約8分の1と、さらに期待を集めています。ところがこの素材、原材料は日本産が世界の約6割を占めているにもかかわらず、加工技術が国内にはとぼしく、ほとんどが海外で製品化されているのです。ものづくり大国日本のイメージからは真逆ですよね。中国では炭素繊維の埋設管がすでに使用されており、何年もメンテナンス不要な生活インフラが整っている事実からも、日本は大きく遅れていると言えます。現在、国内企業と協力し、15mスパンほどの炭素繊維製構造体を製造方法を検討しながら設計中です。ここで技術を獲得することにより、炭素繊維が国内でもさまざまな構造物に活用できるようになること、ひいてはものづくり大国日本の復権に少しでも貢献できればと思っています。

炭素繊維リングの試験後の写真

チタン和釘の製造工程
SDGsを達成するヒントが、ここにはたくさんある。
今の日本の教育現場は、いわば「教科書を与え、それを覚える」のルーティンのなかで優秀さを競っている状態です。これは、本校、そして本科で大切にしていることとは異なっています。ここでは、世の中で起きていることを自分で見て、理解して、問題点を捉え、解決策を考え、行動していく……そんな主体的な問題解決力(デザイン力)を身につけてもらうための学びを提供しているつもりです。教科書を読めば成果が得られる研究など、大学にはひとつもありませんから。
本科で言えば、建築士などの資格を取ることも確かに大事です。でも、資格は問題解決の一手段でしかありません。SDGsをはじめとした日本の、世界の諸問題に、自分ならどうやって立ち向かっていけるのか。それを考えるためのヒントが、本科にはたくさんあるということなのです。