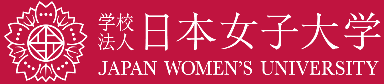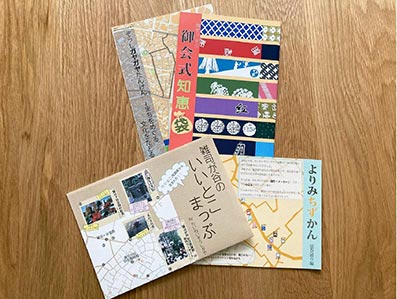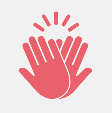学園にまつわる人々の青春時代を、思い出の写真から紐解くアオハルプレイバック。前号の黒岩亮子先生から引き継がれたのは、家政学部の薬袋奈美子先生です。
薬袋先生は附属中学、高校を経て1992年に本学家政学部住居学科を卒業。東京都立大学大学院工学研究科で修士課程・博士課程を修了されました。
附属高校時代に1年間のオーストラリア留学を経験し、「大学時代は毎年、海外に出ていました。4年の卒論発表会の翌日には成田空港にいました」というバイタリティあふれる学生時代を過ごされました。
アジアのスラムでのまちづくりを通して、住民参加の住環境づくりに興味を持ち、多彩な地域、諸国の都市計画を研究しながら、生活者の視点で住環境を分析し、その環境をより良くするための研究活動を行なっています。
現在、力を入れているのは、住宅地内の道路を生活の場とする“ボンエルフ”を日本にも導入すること。規制や法律、日本人の価値観などと向き合いながら、しなやかに活動されています。